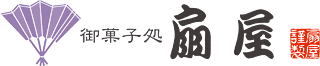さくら餅(小豆こし餡入り)

さくら餅は、長命寺の門番が享保二年(一七一七年)に、向島、隅田川の土手の桜葉を集めて塩漬けにし、
これで「さくら餅」を作ったのが始まりといわれています。
現在、さくら餅に用いる桜の葉は、大島桜の若葉で、それを塩漬けにすると特有の香りが生まれます。
桜葉の塩漬けに調和した餅の香りが餡の旨さを際立たせ、いつまでも心ひかれることでしょう。
草餅(つぶし餡入り)

平安時代に中国から伝来した唐菓子の一種にくさもちいと呼ばれた餅菓子があり、
これは現在の草餅とかなり似たものだったようです。
三月三日の上巳(じょうし)の節句が伝来して日本でもこの日に人形を流したり、
蓬(よもぎ)を入れた餅を食べたりして邪気を払う風習として浸透しました。
蓬はキク科の多年草。古来より煎じて飲んだり、傷口につけるなど薬草として多用されています。
また、京都・大阪では蓬餅、江戸では草餅と呼んでいたそうです。